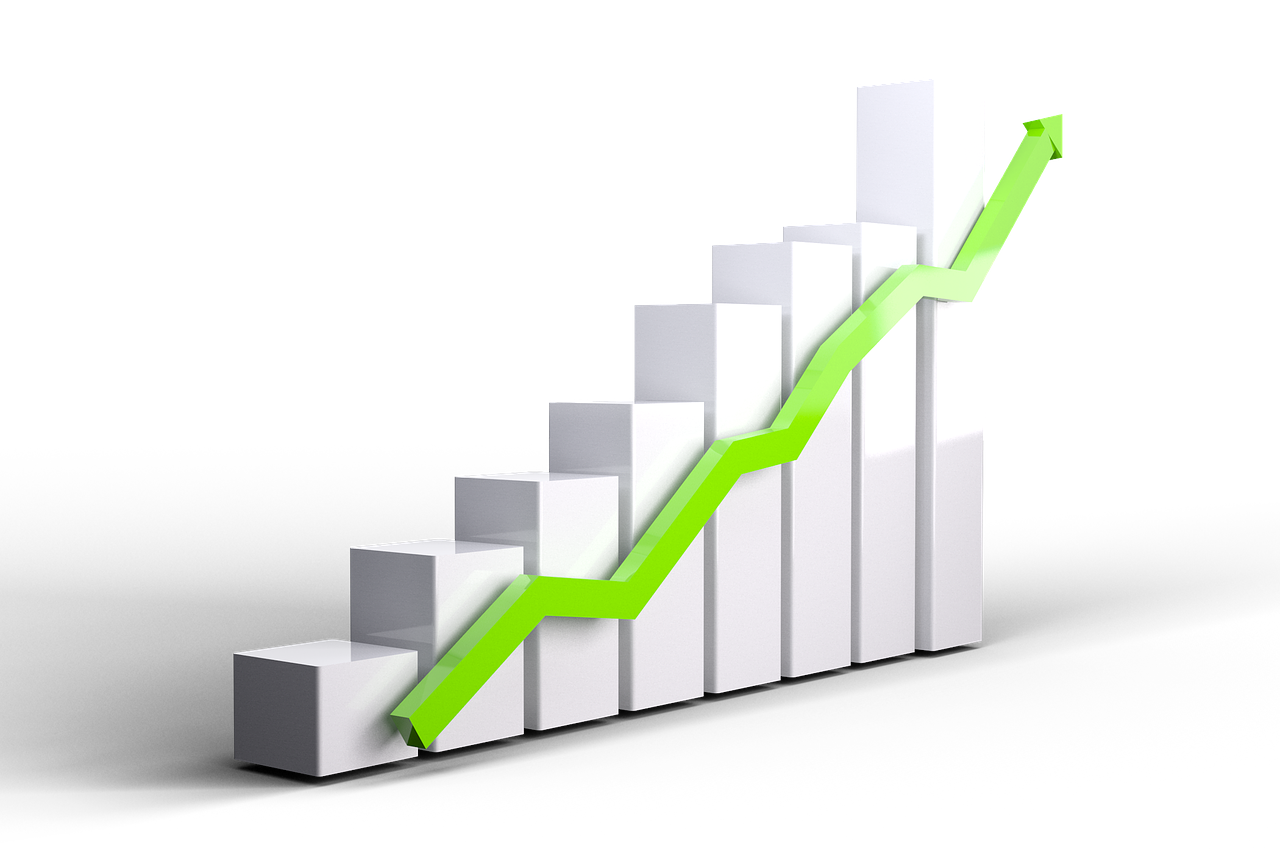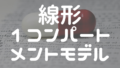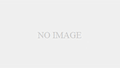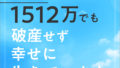どうも、奨学金1500万プレイヤー阪大生のPEN(@PENwitmi)です。
このページを見ているのは、薬剤師国家試験の勉強をどうやって進めればいいのか悩んでいる方でしょうか。
特に勉強始めたてのときは、「あんな膨大な量の青本、どこからどう手を付けていいのかわからない…」というのが本音だと思います。
それはたぶん、全員共通の悩みのはずです。
今回は、薬剤師国家試験の対策の勉強のコツと順番についてお話します。
塾講師として10年間高校生を指導してきた経験と、自分の薬剤師国家試験の経験を基に記事を書きました。
薬剤師国家試験と、効率のいい勉強
国家試験対策は長期戦で、効率ゲー
国家試験の対策は、定期試験対策とは違って、長期戦です。
国公立勢でどれだけ短かったとしても、2ヶ月はフルに勉強を続けることになります。
長期戦の勉強は、戦略と効率次第で大きな差がついてしまいます。
長期の勉強こそ、効率良く進めることが大切です。
期間が1週間しかない勉強だとしたら、どれだけ効率よく勉強しても、それほど差が開きません。
多少効率が悪くても、努力でなんとかなる差しか開きません。
これが1か月、半年…と積み重なっていくと、どう頑張っても追いつけないような圧倒的な大差が開いてしまうのです。
もう一度言いますが、薬剤師国家試験の対策は、長期戦です。
この長期間を、どれだけの効率で勉強し続けられるかが、合否のカギです。
効率のいい勉強とは
薬剤師国家試験対策としては、長期間「効率のいい勉強」をしたいところです。
ここで「効率のいい勉強」について軽くまとめておきます。
「効率のいい勉強」として、大切な軸が3つあります。
それは次の3つです。
継続性=モチベーション×簡便性
「①ずっと継続できる」は、いろんな要素が絡み合っていて実は一番難しいのですが、一番重要な項目です。
ダイエットなど別のものに置き換えると分かりやすいと思います。
究極にシンプルにすると、継続性=モチベーション×簡便性です。
ここでいう簡便性は、「自分にとってそれがどれだけ努力せず自然にできるか」です。
どれだけモチベーションがあっても、面倒すぎることは長続きしません。
どれだけ簡単なことでも、モチベーションが無かったらできません。
モチベーションは、危機感でも構いませんし、純粋に楽しさでも構いません。
将来の自分の年収や、ステータスなどのわかりやすい欲望と繋がっていてもかまいません。(むしろその方が分かりやすくていいです)
モテたいという気持ちから始まる趣味や習慣は、結構多いという話もあります。
何であれ、モチベーションと簡便性の二つが兼ね備わったとき、継続性が生まれてきます。
成果に繋がらない勉強は、一切評価されない
「結果ではなく、頑張った過程を評価してほしい」という主張を耳にすることがあります。
特に受験時代では「評定」というものがありましたから、宿題をきちんとやっているか、出席しているか、といった「過程」を評価されることもあったでしょう。
しかし、薬剤師国家試験では、そのような考え方は捨ててしまうことをオススメします。
その考え方自体を比定するつもりはありませんが、国家試験には過程を評価する項目が一切ありません。
どれだけ頑張っていようが、点数が取れなければ不合格。
薬剤師になる資格はないのです。
そういう試験の場合は、「成果につながらない勉強は、一切意味がない」と割り切ってしまうほうが、最終的には幸せになれると思います。
継続できる勉強法を見出して、それを3か月続けたとしても、成果(点数)に繋がっていなかったら意味がない、ということを念頭においてください。
具体的な勉強法は、こちらを参考にしてみてください。
シナジーは+αの効率
①ある程度継続できて、かつ②成果につながる勉強を一定期間続ければ、それは十分効率のいい勉強と言えます。
実はその段階までいくことが、一番難しいのです。
しかし、この2つの基本を押さえてからも、更に効率を上げることは可能です。
それが③のシナジーを生む勉強です。
一言で説明するのは難しいですが、めちゃくちゃシンプルに言うと「1つ覚えて3回得する」ような勉強です。
例えば、生物の分野を勉強すれば、薬理や薬物治療の理解が深まることがあります。
これはシナジーを生んでいる分かりやすい例です。
これが生物ではなく物理だとしたら、シナジーを生むのは一気に難しくなります。
ギブズエネルギーの勉強をして、「だからこんな病気や薬があるのか…!」となる人はそうそういないでしょう。
効率のいい勉強をするためには、シナジーを生みやすい範囲から勉強をするとよいですね。
代表的なのは、生物、薬理、病態・薬物治療です。
慣れてくると、衛生や法規などでもシナジーを生み出すことができるようになってきます。
こちらの記事もあわせて読むと、理解しやすくなると思います。
薬剤師国家試験の勉強のコツ

自分の勉強スタイルを確立している人は、その勉強スタイルで貫き通すのが一番リスクが少なく、継続できると思います。
ここから先は、自分の勉強スタイルや方法に自信がない人向けの内容です。
苦手な分野から手を出さない
「苦手な内容は克服するのに時間がかかるから、早めから始めておく」
これは正しいようで、実はかなり微妙な意見です。
苦手な内容から始めてしっかりと効率よく勉強できるのは、よっぽどモチベーションが高いか、めちゃくちゃ生真面目かのどちらかです。
つまり、苦手な分野というのは、継続性の要素である「簡便性」が弱いのです。
勉強を始めるのに、勢いだとか気合いが要るような勉強は、めちゃくちゃ効率が悪いです。
勉強で一番苦しいのは、ダラけているのを辞めて、机に向かって座るまでです。
ここを乗り越えにくい勉強は、そもそも継続するわけがないのです。
やる気やモチベーションでカバーしないといけない時点で継続性に乏しく、中途半端に自己嫌悪に陥って終わる確率が非常に高い。
「苦手な内容は克服するのに時間がかかるから、早めから始めておく」というのは、大体は経験談ではなく後悔です。
(私は出来なかったけど)というのが後ろについてくると思ってください。
正しくは「苦手な内容は克服するのに時間がかかるから、早めから始めておけばよかった」でしょう。
そういったほとんどの人は「早めから始めることそのものがメチャクチャ難しい」から、できなかったわけです。
始めるためにエネルギーを使っても、結局成果につながらなければ意味がありません。
それなら、やりやすい科目から始めるのがリスクも低いです。
ちなみに、直前期まで放置していても、危機感からくる圧倒的モチベーションで、とんでもない効率で勉強が進みます。
苦手だろうが何だろうが、直前になればやるしかなくなりますから。
思い切ってそこまで放置するのも悪くありません。
(私はそのタイプです)
テストが始まる2週間前と12時間前では、効率がかなり違うのを知っている人も多いでしょう。
「直前まで放置したら後から大変だ」とわかっていても放置してしまう、というのも、ご存知だと思います。
実はそれは、長期戦においては悪くない選択なのです。
武器科目を作る
先ほどと同じことを言っているようですが、国試対策を始めるならまず得意な科目や好きな科目から始めましょう。
大きく2つの理由があって、
1つは、自分では得意だと思っていても、たいていは必要レベルに達していないこと。
もう1つは、圧倒的に効率がいいこと、です。
いくら得意科目とはいえ、無勉で合格者上位に食い込むほどできる科目というのはそうそうありません。
得意科目には、苦手科目で落としてしまった点数を補ってもらう必要があるので、合格者平均程度の点数では全然足りません。
そのレベルまで得意を伸ばすことで、心の余裕が生まれてきます。
また、得意科目の勉強は、勉強を始めるまでのハードルが非常に低いです。
特に好きな科目であれば、不必要な知識までたくさん覚えてしまうこともあるかと思います。
これが、記事の最初で言った「効率のいい勉強」の理想的な状態です。
できるだけ暗記せず、興味関心を持つ。
世の中には、数学の公式は覚えられなくても、アイドルグループ全員の名前やイメージカラー、誕生日から年齢まですべて暗記しているという人がいたりします。
勉強が出来ない人というのは、勉強が苦手なんじゃなくて、勉強に興味がないだけです。
逆に勉強が出来る人の多くは、その内容に興味があるだけ、というのが多いです。
理科が得意な人に「なんでそんなこと知ってるの?なんで覚えてるの?」と聞くのは、
「なんでそのアーティストのCDアルバムタイトルとか、曲順覚えてるの?」と同じようなこと。
そもそも覚えようとして覚えているわけでもなかったりします。
私としては、野球選手の守備位置や背番号、異動歴、打率を覚えることよりも、化合物の化学式や化合物名を覚える方がはるかに簡単です。
これは純粋に、私が野球に興味がないだけですね。
このように、人の記憶は、興味関心と強烈に結びついています。
では、これまで勉強に興味が無かった人が、興味関心を持つにはどうすればいいのでしょう。
ちゃんと方法があります。
それは、勉強の軸を「教科書の内容を覚えること」から「その事柄を理解すること」にシフトすることです。
「え、なんで?」
「どうやって?」
といった純粋な疑問に答えるように勉強を進めるのが、一番の近道です。
興味ないことは興味がないままでいいのです。
まずは興味がある、もしくはまだ関心が持てる内容から勉強を始めたいところです。
興味を持ちやすい範囲は病態・薬物治療
薬剤師国家試験の範囲の中でも、最も日常生活に関連して興味を持ちやすいのが、病態・薬物治療の科目です。
身近に何か疾病にかかっている人がいれば、その疾病と治療薬について深く調べてみる。
何か飲んでいる薬があれば、併用禁忌薬やCYP代謝について調べてみる。
様々なアプローチが考えられます。
もしくは、「なりたくない病気」から調べてみるのもいいでしょう。
例えば「将来乳がんになったらどうしよう」と心配なら、まずは乳がんになる成因から調べてみる。
もしなってしまったら、どんな治療が待っているのか、今の年齢ならどんな薬を飲むことになるのか。
そうやって当事者意識を増やすことが、自然と興味関心につながります。
そうやって一つの疾病について深く知ったら、それに関連した薬や疾病についてどんどん調べていくといいです。
関連していなくても、興味さえあれば構いません。
知識の森を作る
薬剤師国家試験の勉強を、森林つくりに例えてみましょう。
勉強のコツとして、とにかく最初は、知識の木を増やすことが重要です。
適当にでもとにかく木を増やせば、気づけば森になっていきます。
一番失敗しやすいのは、「土台が大切だから」と言って、すべての面積の土壌を耕そうとすることです。
一番退屈な作業を、延々と続けるのは、非常に困難です。
おそらく、一つの苗を植えることもなく、植林計画は失敗します。
とりあえず木を植えてみて、木の成長を楽しんだり、木の間に鳥が行き来しているのを見たりして、やる気が増してくるものです。
できることから着実に一歩ずつ。
まずは、一番モチベーションが出やすくて、継続しやすいことから始めてみてください。